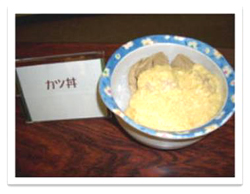「食べるということ」
| 【摂食嚥下障害看護領域】 愛知県立がんセンター病院 青山寿昭さん | |||
 |
看護師16年目、摂食・嚥下障害看護認定看護師をしています。飲み食いが好きで、摂食・嚥下に興味を持ったのは8年ほど前でした。 平成18年に人の勧めで認定看護師になりました。勤務先は愛知県がんセンター中央病院で主にがん患者への嚥下障害に関わっています。 | ||
| Vol.1 2009年7月 | 「食べるということ」 | ||
|
はじめてエッセイを書きますが、まず自己紹介ですね。 昭和47年生まれの36歳、落着きがないのかよく若く見られます。 看護師になり15年、初めは救命救急に興味がありましたが、 何故かずっと愛知県がんセンター中央病院で働いております。 現在の病棟は頭頸部外科病棟で9年、認定看護師になり3年が過ぎました。 食べることが大好きで摂食・嚥下障害に関わるにはちょうどいいかもしれませんね。 摂食・嚥下障害看護認定看護師の仕事は施設によって全く異なります。 病院にいる職種や患者さんによって変わってきます。 僕はがん患者さんを中心に嚥下障害と関わっていますが、 一番多いのは頭頸部癌術後次いで食道がん術後の患者さんです。 機能の評価と訓練の立案、食形態の調整や栄養評価などもやっています。病院内の「飯屋」ですね。 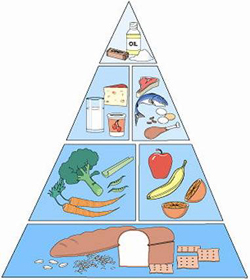 僕にとっての食べる事、まず真っ先に出てくるのは楽しみです。
僕にとっての食べる事、まず真っ先に出てくるのは楽しみです。美味しいものはお腹が膨れていても食べたいと感じてついつい食べてしまいます。 でも学生への講義の中で食べる事の意義を尋ねると真っ先に返ってくる言葉が栄養補給でした。 看護の勉強をしている学生がいきなり食事の意義と言われても「楽しみ」とは返答できないでしょう、 教科書にも第一に楽しみとは記載されていないのではないのでしょうか。 栄養摂取といえば病院の職員食堂の食事がどうしても口に合わないのです。 仕事中に腹が減っては困るので業務的に食事を済ませます。 本当はせっかくなので楽しみたいのですが、栄養摂取だと感じる瞬間です。 空腹を感じて食事を摂取する、この行為は一見栄養補給に感じますが、 摂取する食事にはこだわりますよね?単なる栄養補給であれば何でも良いわけですが、 まず好みが先行し、おおげさを言えば好みが無ければ食事を抜く人もいます。 実際に患者さんでも嚥下食が美味しくないといって食べてくれない患者さんもいます。 しかし飢餓に苦しむ地域ではそんな事は言っていられません。 現在の日本社会において食事の意義というのは栄養摂取よりも楽しみの要素が強いと感じます。 |
|||
|
|
|||
楽しみの要素を盛り込んでコミュニケーションをはかる事にも利用しますよね。
コミュニケーションの場には食事が関係する事が多いと思いませんか?
例えば僕がデートに誘うときは「一緒に食事でも」「飲みに行きませんか」などをよく使用しました。
食べる事ができなかったらコミュニケーションをとる場を作るのにも苦労しただろうし、
やはり美味しいものを食べると気分が良くなり結果も良かったのではないかと振り返る事ができます。
ですが、食べる事が楽しみであるのは美味しい事が前提です。
嫌いなものはどうでしょうか?僕は嫌いなものは嚼まずに丸呑みするか息を止めて食べます。
それは味を感じてしまうと飲み込めないからです。
美味しくないのにいつまでも口の中に滞在して味を感じる、皆さんも経験があると思います。
もし嚥下障害の人が「飲みたくない」「嚼みたくない」と感じる食事しか出てこなかったら
より経口摂取が難しくなりますね。嚥下食は常食よりも美味しくないといけないと思っています。
患者さんに食べる楽しみを提供するためには美味しい食事を提供できる環境も重要だと感じています。
友達の管理栄養士さんがその思いで作ったソフト食を載せてみます。
どちらもカツ丼をイメージしていますが、写真1は冷凍食品です。
食事をする事で脳が活性化され表情が良くなったり、食べる事で目・手・口などの協調運動が改善されてADLが拡大したり、満足感や充実感で生活意欲が向上したり、さまざまな側面から改善して経口摂取を開始すると表情が変わった患者さんもたくさんいます。 僕は恩師から「食」という字は人を良くすると書くと教わりました。 そんな患者さんと出会うと本当に食事というのは人生で大きな役割をしているのだと感じます。 食べるのが好きなだけに自分にあった「職」かもしれないと思っています。 全ての人に口から食べるチャンスを与える事ができるよう、日々精進したいと思います。 |
|||