「食べるということ」
| 【摂食嚥下障害看護領域】 愛知県立がんセンター病院 青山寿昭さん | |
 |
看護師16年目、摂食・嚥下障害看護認定看護師をしています。飲み食いが好きで、摂食・嚥下に興味を持ったのは8年ほど前でした。 平成18年に人の勧めで認定看護師になりました。勤務先は愛知県がんセンター中央病院で主にがん患者への嚥下障害に関わっています。 |
| Vol.10 2010年8月 | 「窒息」 |
日本人が窒息しやすい食品が餅であることは有名ですね。しかし他の食品はどうでしょうか?東京消防庁の発表を参考に窒息が多い食品を調べてみると、ご飯・寿司・パン・肉類・あめ・団子・ゼリー・流動食などでした。日本人の主食が多くて驚きますが、高齢者の唾液が減少して乾燥した口腔では、喉に詰まりそうなイメージは持てますよね。ただ、ゼリーや流動食はちょっと不思議な気がしますが、そういうものしか食べることができない嚥下障害の方だと推測できます。窒息しやすい食品としては国柄があり、アメリカではフライドチキンやハンバーガー、ステーキなどがあるそうです。日本人の高齢者はフライドチキンやハンバーガーを食べることが少ないですので件数は少ないのでしょうね。その他、メキシコではタコスであったり、イタリアではピザであったりするようです。いずれも日本で簡単に食べる事ができる物ですので気が抜けませんね。ちなみにこんにゃくゼリーの窒息の危険性は食品安全委員会で公表されています。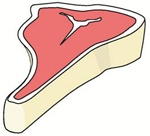 窒息は自宅だけではなく病院や施設でも起こります。僕の病棟でも10年ほど前にはっきりした原因は分かりませんが、窒息で亡くなった患者さんがいます。呼吸状態が悪く緊急入院した患者さんでした。年齢も60歳前後で明らかな嚥下障害はなく全粥食が提供されました。今考えると、呼吸状態悪化が原因で入院した患者さんへの食事は十分検討する必要があったのでしょう。それは呼吸と嚥下は深くかかわりがあるからです。嚥下するときは呼吸を止めますし、それには飲むために呼吸を整えねばなりません。しかし、普段はそんなことを気にもしていませんよね。例えば、マラソンをしている最中に水などを飲み込みにくいと感じたことはないでしょうか?マラソンしている最中は呼吸回数が多くてタイミングをとり辛かったり、呼吸を止めるので息が苦しかったりすると思います。呼吸困難がある患者さんも同じで、さらに口腔機能が低下していたら吸気とともに喉に吸い込まれる可能性もあります。当時の僕には推測すらできませんでしたが、呼吸回数が多く呼吸と嚥下のタイミングが崩れて嚥下しにくい状態で食事をしたために、誤嚥して窒息したとも考えられます。何気なく提供している食事ですが、患者さんが入院した時の最初の食事摂取状況を把握する事は大切だと感じています。
窒息は自宅だけではなく病院や施設でも起こります。僕の病棟でも10年ほど前にはっきりした原因は分かりませんが、窒息で亡くなった患者さんがいます。呼吸状態が悪く緊急入院した患者さんでした。年齢も60歳前後で明らかな嚥下障害はなく全粥食が提供されました。今考えると、呼吸状態悪化が原因で入院した患者さんへの食事は十分検討する必要があったのでしょう。それは呼吸と嚥下は深くかかわりがあるからです。嚥下するときは呼吸を止めますし、それには飲むために呼吸を整えねばなりません。しかし、普段はそんなことを気にもしていませんよね。例えば、マラソンをしている最中に水などを飲み込みにくいと感じたことはないでしょうか?マラソンしている最中は呼吸回数が多くてタイミングをとり辛かったり、呼吸を止めるので息が苦しかったりすると思います。呼吸困難がある患者さんも同じで、さらに口腔機能が低下していたら吸気とともに喉に吸い込まれる可能性もあります。当時の僕には推測すらできませんでしたが、呼吸回数が多く呼吸と嚥下のタイミングが崩れて嚥下しにくい状態で食事をしたために、誤嚥して窒息したとも考えられます。何気なく提供している食事ですが、患者さんが入院した時の最初の食事摂取状況を把握する事は大切だと感じています。
|
|
|
|
|
食事の摂取状況はいろいろととらえ方があります。例えば、常食を50%摂取したというのをどう考えるでしょう?「食欲が無いが50%は常食を摂取できる」と「何か食べにくいものがあって50%しか摂取できない」では意味が違ってきます。食べにくく、苦手なものがあって摂取できないのであった場合、当然誤嚥や窒息の危険性が増しますので、食形態や栄養摂取方法を検討せねばなりません。以前、ある先生に「常食ってなんですか?」と聞かれました。僕は「常食」って日常的に食べている食事だと思い浮かびました。でも、よく考えると若年者と高齢者では日常的に食べている食事は違いますよね。病院によって差はありますが、一般的に入院患者さんは高齢者の方が多くなりますので、高齢者向けの食事である必要があります。さらに年齢を考えると、高齢化社会に向けて常食を考え直す必要があるのかもしれませんね。入院して何気なく食事を提供していますが、嚥下障害の自覚がない患者さんも少なくありませんので、食物形態や栄養方法には注意が必要だと思っています。そして、食事の摂取状況の把握をし、窒息や誤嚥の危険回避をせねばなりません。 窒息した場合の対処方法は吸引やハイムリッヒ法が一般的です。ハイムリッヒ法は患者さんの後ろから処置者の両腕を前に回し、みぞおちの下で片方の手を握り拳にしてもう片方で腕を組み、腹部を情報へ圧迫するという方法です。この方法は立位でも座位でも使用できます。窒息は嚥下機能が悪い方だけではなく小児でも耳にします。窒息させないことが重要ですが、一刻を争う事態ですから常に対応できるようにしておく必要があると思います。
窒息した場合の対処方法は吸引やハイムリッヒ法が一般的です。ハイムリッヒ法は患者さんの後ろから処置者の両腕を前に回し、みぞおちの下で片方の手を握り拳にしてもう片方で腕を組み、腹部を情報へ圧迫するという方法です。この方法は立位でも座位でも使用できます。窒息は嚥下機能が悪い方だけではなく小児でも耳にします。窒息させないことが重要ですが、一刻を争う事態ですから常に対応できるようにしておく必要があると思います。 |
|
